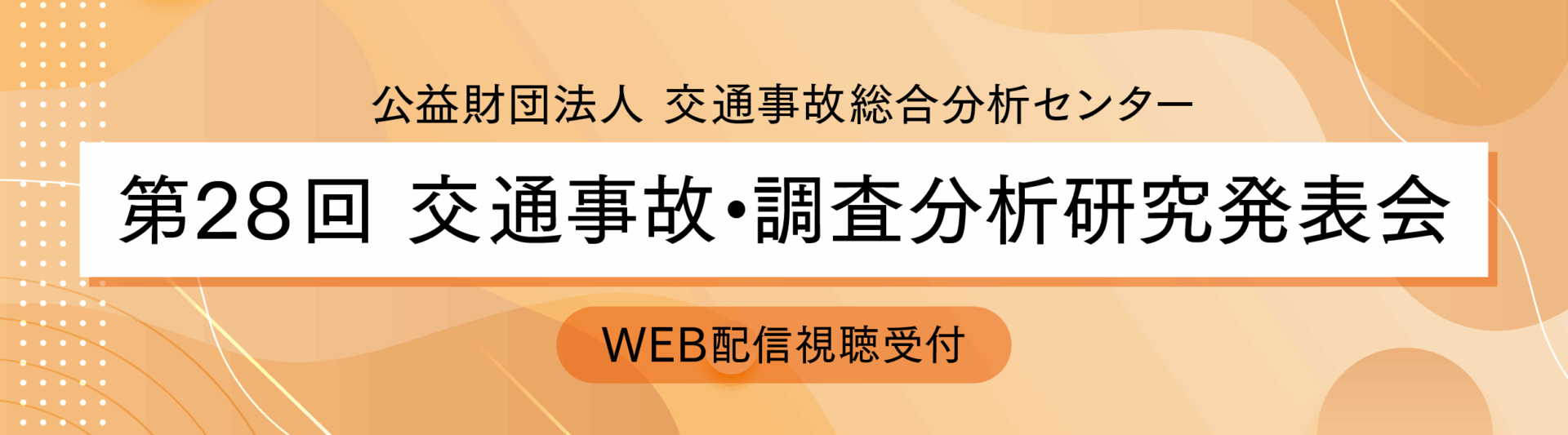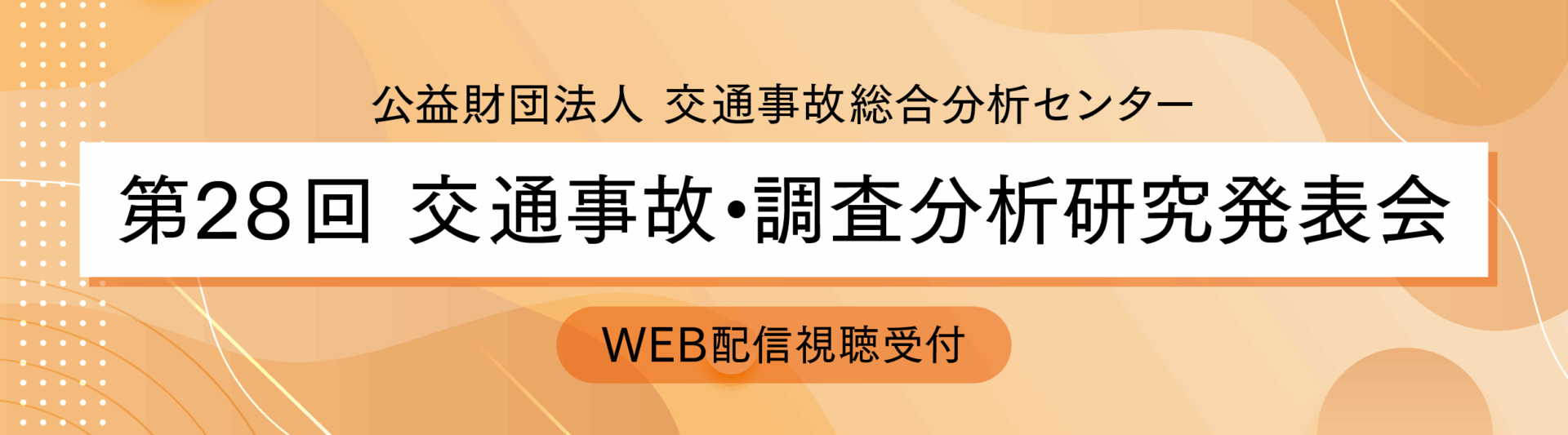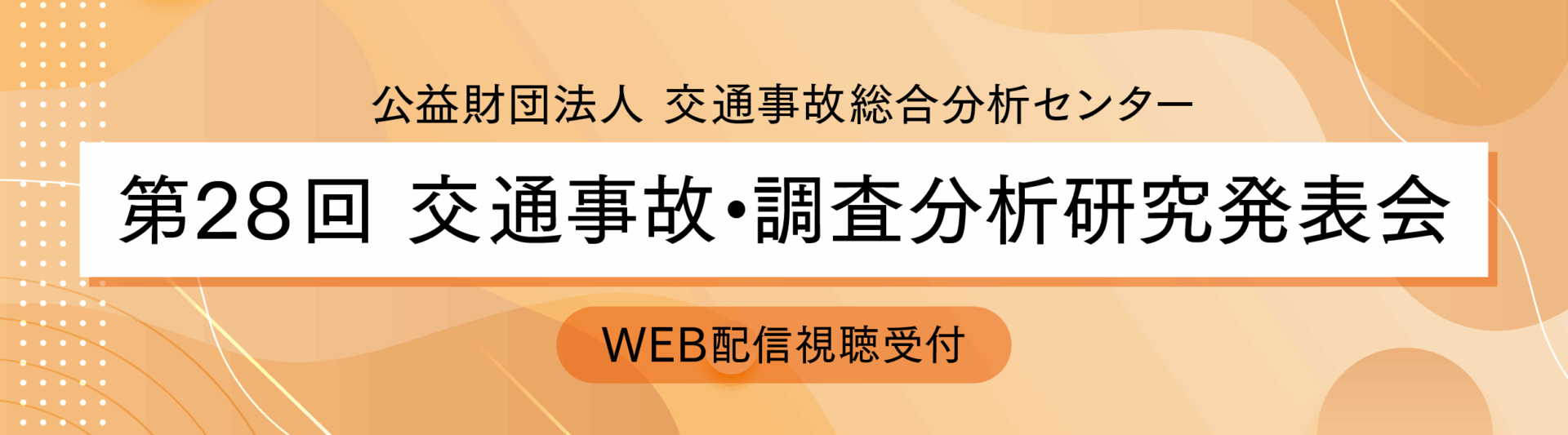本アーカイブは、Vimeoを使って配信いたします。VImeoの推奨視聴環境は以下になります。
パソコン
・Windows 10 以上 / macOS 10.13 以上
・最新版の Chrome / Edge / Firefox / Safari
※ Internet Explorer には対応していません。
・安定したインターネット接続(有線LAN推奨)
スマートフォン・タブレット
・iOS 16 以上 / Android 8 以上
・Safari または Chrome
・Wi-Fi または 4G/5G 推奨
【ご注意点】
・会社のセキュリティ設定やファイアウォールによって視聴できない場合があります。
その際は、別のネットワーク(モバイル回線や自宅Wi-Fi)での視聴をお試しください。
※ モバイル通信ではデータ通信量が多くかかりますのでご注意ください。
・視聴には下り速度 5Mbps 以上を推奨します。
・ネットワーク環境によっては映像が止まる場合があります。
その際は画質を下げるか、別の回線でお試しください。